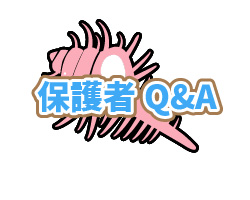高いところに登るんです
前回の「またぐ」動作と似ていますが、こちらも多くの保育施設で寄せられる悩みです。
特に0,1,2歳児クラスでよく聞かれます。
ロッカーや絵本棚に登って危険!!そして対応と負の連鎖に・・・。
登ることを止めてほしいと思い、子どもに声をかけ、それでも繰り返すと大人の安心・子どもの安全のためと思って、ロッカーなど登る場所を撤去し広い保育室にしてしまうことがあります。実は、その対応が子どもたちの欲求に更に刺激し、ロッカー以外にも些細なところに登れる個所はないかと探して「挑戦」するようになります。ただし、大人にとっては「止めてよ~」という負の連鎖に陥りやすくなります。
侮るなかれ!0,1歳児の身体能力と対応力!!
特に0,1歳児クラスでは些細な段差は危険として認識されやすくなります。しかし、10カ月ほどの高這い期のお子さんはも自分の胸くらいの段差をよじ登るようになります。ハイハイ期のお子さんでも急な傾斜を慎重に、確実に登っていきます。


登れるけど危険じゃないの??
自分で登れるようになると、段差などを危険と認識しやすくなり慎重に楽しむ様子が伺えます。しかし、大人が手助けをしてしまうと手順や危険性が感じられにくい状態となります。また、入り口や広さ、子どもが垂直に落下しないための工夫が必要となります。
全員が登れる状態ではなく、発達が到達したり、興味関心が湧いたりした子どもから「挑戦」できる環境となります。
ただし、上記したようにただ、高さや傾斜を作っても重篤な怪我(ハザード)につながるので、環境を整える際は「アイデア」と「議論」が必須となります。
子どもの行動が保育のヒント
このように登る姿は一見、大人には危なっかしい、止めてほしいとなりますが、登る欲を満たせる場所を確保することで満足でき、登ってほしくない場所での活動が軽減されると考えられます。
しかし、ただ登る欲だけはなく、大人の視界を体験したい、あっちには何があるの??、オレを見てくれ!!!!といった姿が隠れているため、まずは子どもの情報を把握してからどんな環境や関りが良さそうかを考えていきましょう。
「遊道」では環境整備についての共通理解を保育者にお伝えした上で、子どもたちの状況からどのような環境・関りが良さそうかご提案させていただきます。