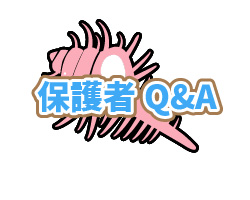部屋を区切ったけれど安心できない
保育環境を視察する中で、「安全」のためと思って、部屋を区切り子ども達を「見ている」状態を作る保育施設が多いと感じております。しかし、いくら部屋を区切っても、保育者の「不安」は常に発生し、更に子ども達も欲求と不満から余計活動的になり、大人も子どもも安心できない場所になってしまいます。
ここでお伝えする区切りとは、例えば1歳児クラスで1部屋の中で子どもが移動できないように柵で区切って活動範囲を制限するようなことです。
また、区切らずとも、一つの狭い空間(保育室)に子どもを入れておくことも同様です。なぜ、「子どもを見守れ、安心できるように」した工夫が「不安」となってしまっているのか、紐解いていきましょう。
子どもを見守れるように工夫したのに不安が強い
せっかく部屋を区切っても、子ども達は走り回るし、大泣きして、またトラブルが起こりやすくなって対応に手が取られ、これではもっと保育者を増やしてもらわないと!!と悪循環になっている保育施設は少なくありません。
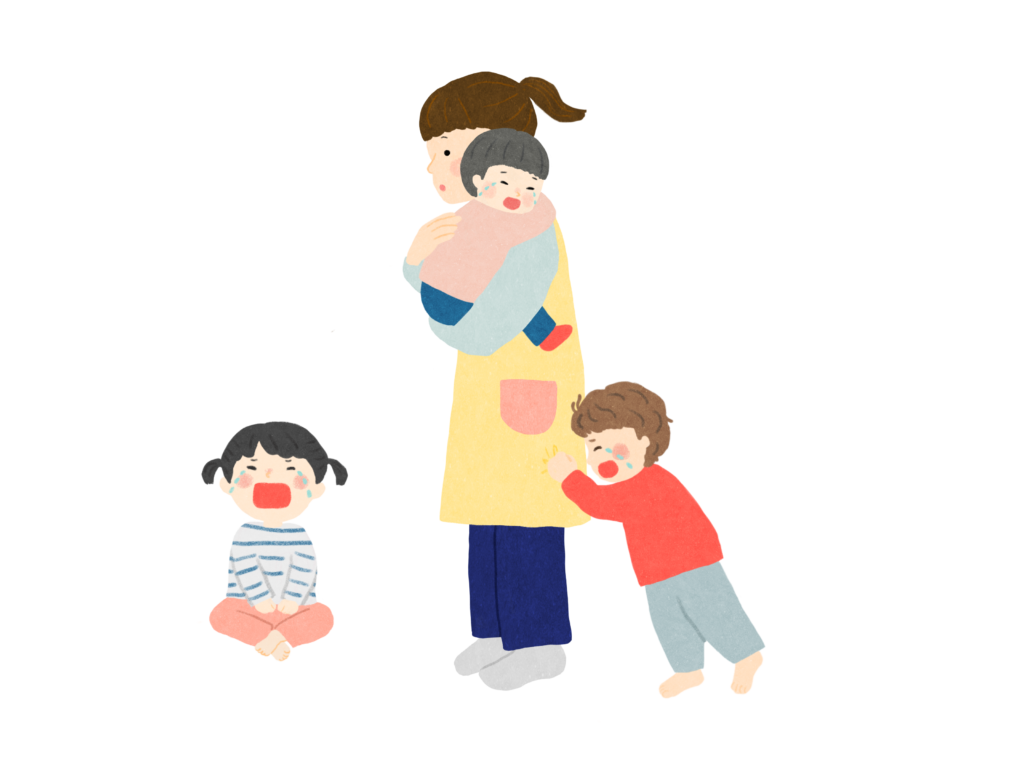
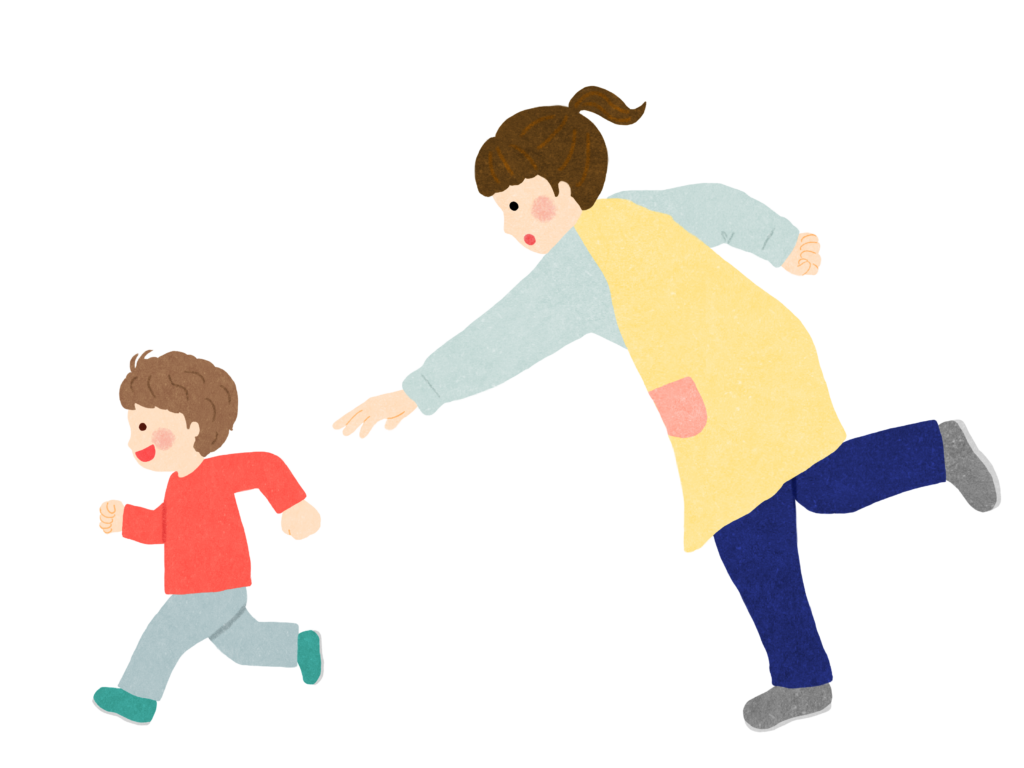
子どもの気持ちになってみよう 区切られている(制限)ことで
〇探索欲求が満たされない。走り回りたくなる。登りたくなる。入ってほしくない場所へ行く。
〇子どもの密度が高くなり、トラブルになる。イライラの充電。
〇子どもの密度が高くなり、じっくり遊べない。
〇子どもの密度が高くなり、不安を感じる子どもの感度が増す。
〇おもちゃの数が制限され、「今やりたい」が見つからない。「暇」状態へ。
など。
区切る空間(狭い空間)=安心を一度考え直してみよう
部屋を区切るのではなく、コーナーを多目に配置して、遊びが見つけられる空間を作ることをおススメしております。
好きなコーナーに集う子どもたちは、イライラを充電よりも遊びがもっと楽しくなるように情報を収集することになります。
また、コーナーを設置することで、子ども達が分散されじっくり遊び込めることが期待できます。


保育者の声
以前、一級建築士・こども環境アドバイザーの井上寿さんが沖縄県の保育施設に巡回された際、広い保育室で子どもを見るためと区切っていた保育者さんに、上記の提案をしたところ、部屋を広く使いコーナーを活用した方が(遊びが選べる状況)「子どもが分散し、大人が安心できた」という言葉が印象的でした。
子どもの姿からヒントを得よう
しかし、ただコーナーを作っても、目の前の子ども達に合っていなければ「暇」状態になってしまうことがあります。
日々、子ども達を観察し、何をやりたがっているのか、子どもの姿を基に環境整備を試行していきましょう。
「遊道」では、子ども達・保育者・保育環境からそれぞれの特色に合わせて保育を提案させていただきます。